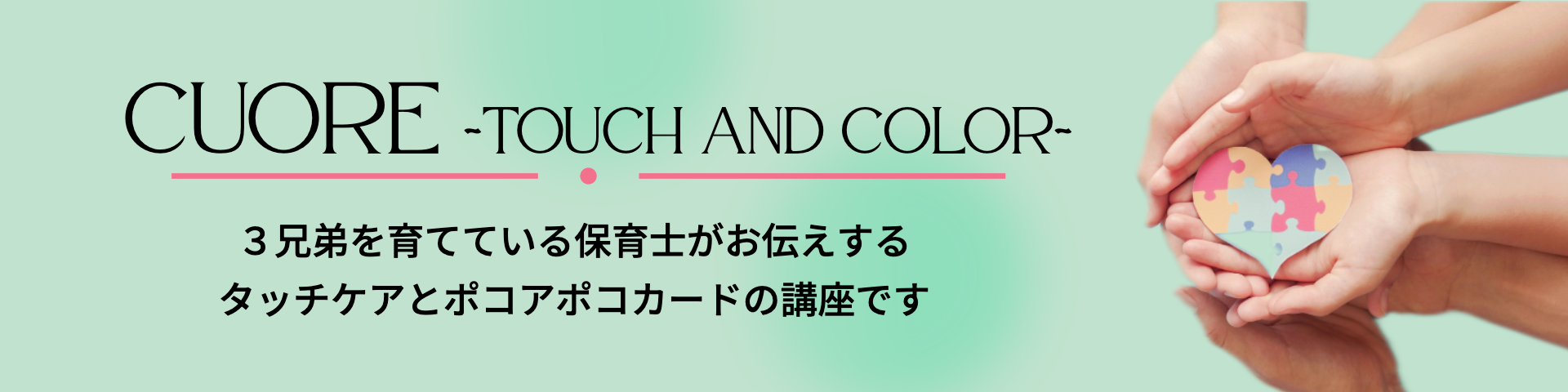(2019年2月にアメブロに投稿したエピソードをまとめ直した記事です。)
目次
子どもへの責任、負いすぎていませんか?
自分もしかり、ですが。
家で子どもを一人で世話していると、『私が何とかしないとこの子は…。』というポリシーのもと、真っ直ぐ伸びる竹のごとき子どもを「あーでもない、こーでもない」と時には無理やりひん曲げ、時には少しでもより良い環境をと、あっちこっちに植え替えて(竹はそんなのむりでしょうが)なんとか大きくしようとしている感じ、やってませんか?で、成果出ず母だけヘトヘト…。
私は教員時代、似たような経験をしたことがあります。
初めて幼稚園で勤めてクラス担任になり、
「何とかして私が担任として育てなければ!」
「私がなんとかしなきゃいけないのに!」
「私が!」って。
でも、ある時副園長先生が私に『幼稚園でね、楽しかったー!って1つでも思えることがあればOKなのよ。それはね、他の先生との出来事でもいいの。』って言ってくださった、その瞬間から、肩の力がスーっと抜けた気がしました。
そうだ、私一人しかいないわけじゃないんだ、って。
幼稚園には、担任以外に、他のクラスの先生、フリーの先生、バスの先生、専科の先生、総出で、子どもたちを育てている。それも、それぞれの視点、それぞれの関わり方で。そんな当たり前のこと、すっかり忘れてしまっていたんです。
親以外からの影響も
だからね、子育てに関しても、母親、父親、身近な大人(親戚・先生とかね)通りすがりの大人、で、ざっくり3:3:3:1くらいにその責任を分けるのはどうでしょう。例えば父と母で6くらいは担う。残りの4は周りの環境からの影響。という具合で。
周りの大人の影響力って意外と大きくないですか?
子どもって、通りすがりの大人のこと、結構冷静に見てますよね。
「え、あの人赤なのに信号渡ったよ?」とか
「ここって、タバコ吸っちゃいけないんだよね?」とか大きい声で言っちゃう笑
良くも悪くも、子どもの中に残るわけです。
他にも、ちょっとお友だちの悪いこと真似したり。幼稚園では良くある話です。好きな動画チャンネルの言葉遣いや投稿内容に影響されることも最近は多いですよね。
逆にいい影響もあるわけです。『ママー!YouTubeでね、人の話無視すると悲しいことが起きるって言ってたー!』って4歳になった娘が私に感動を持って教えてくれました。『へー!そうなんだね!』って良いながら、心の中では『それ、何度も私言いましたけどー』って思いました。
こどもは、こうやっていろんなところから吸収しながら、親の判断基準や価値観(つまり、しつけ)と子ども自身が体験して感じたことを照らし合わせて、自分なりの判断基準や、価値観が出来上がっていくんだと思うんです。
今、目の前にいる我が子だって、『片付けはできるようにさせねば!』っていう信念を持って何百回言って聞かせたところでサッパリ響かなかったのに、ふとしたときに友達に言われた一言とか、読んだ本とか、そう言う事から子ども自身の気持ちに変化が起きるかもしれない。
しつけはザクザク
Eテレの【すくすく子育て】で大日向 雅美先生(恵泉女学園大学 学長/発達心理学)も
「しつけはね、ザク ザク で良いんです」ってお話しされていたんです。
子ども自身に、判断基準や価値観が出来上がったとき、スーーっと抜かれるのが、しつけ糸。
一生懸命に細かく縫ってたら、しつけ糸を抜くときに、糸が絡まったり、キツくなったり最悪、布に穴が開いたりしちゃう。
だから、ザクザク。
抜いたあとは自分で縫うし、誰かがもっと的確に導いてくれるかもしれない。なるほどです。
まとめ
そんな感じでね、ママ一人がなんでもかんでも背負わないで、母、父、身近な大人、通りすがりの大人が、それぞれの影響力に自覚をもって、世間の子どもと関わろうとしたら、ちょっと子育てに対する世間のイメージが変わるんじゃないでしょうか。
だからね、ママも、3割にはしっかり責任持つけど、あとの7割はママの知らないところで誰かが、育ててくれている、と信じて、任せてみるのはどうでしょう。それは、我が子の【人を見る目】(誰を信じるか決める、選ぶ力)を信じることに繋がってる気がします。
そもそも、人間につながる生き物は群れで子育てしてきたルーツがあるって言われています。一人で育てるようには出来てないの。群れで育つから、群れで生きていけるようになる。
何でもかんでも親の責任にするんじゃなくて、人間っていう大きな群れの中で子どもを育てていく世の中になったらいいな、と思います。