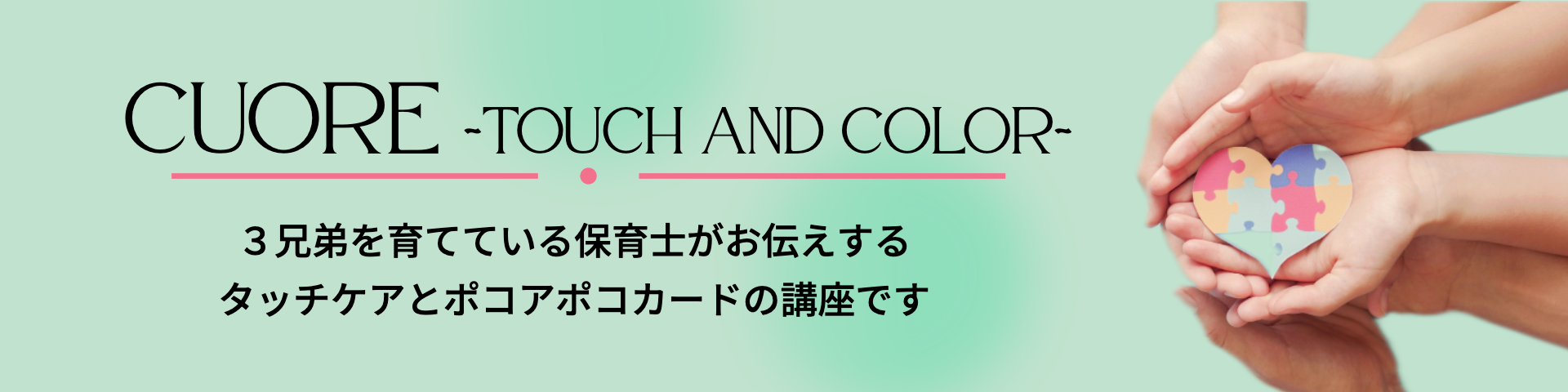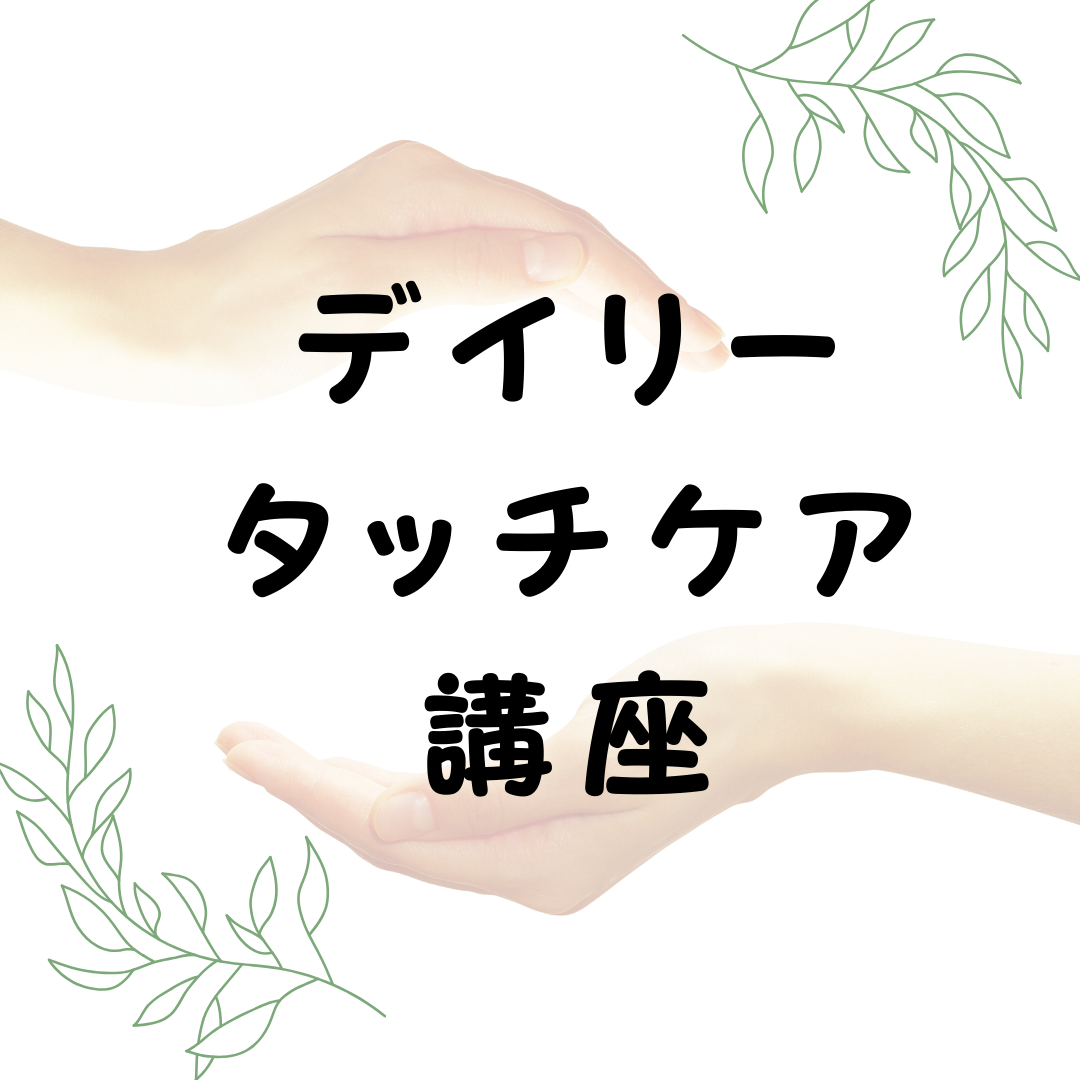久しぶりにタッチケアのお話です。
目次
「触れる」は基本中の基本、ですよね
保育のスキルとして、例えば絵本の読み聞かせが上手くなりたい、手遊びのバリエーションを増やしたい、造形の知識を増やしたい、と思う保育者はとても多いと思います。
一方で、タッチケアの良さをお伝えするときに思うのが
「自分の触れ方に疑問を持つ人は少ないだろうなぁ」「もっと触れる技術を高めたい」と思う人は少ないだろうなと言うこと。
コミュニケーション、特に子育てや保育など、子どもとのコミュニケーションの場面では、自然と体に触れたり、スキンシップを通して感情を伝えようとすることが多いですよね。
転んだ子に「大丈夫?」と言葉だけで伝えるより、
「大丈夫?」と言いながら背中や腕を触る方が
言われた側はより安心するし、慰められる、大事にされている感じがします。

大人も、成長の過程で「触れてもらう」ことで安心したり、より相手の思いを汲み取るできた経験が、自然とそうさせるのでしょう。
あえてどこかで学ばなくても、誰しもが「できる」「できている」と思う、言うなれば「コミュニケーションスキルレベル1」なのが「触れる」ことです。
触れ方って大事。
転んだ子どものケアとして子どもに触れるとき、どんな触れ方をしているか、意識したことはありますか?
実は、安心させようと触れていても、触れ方次第では触れる側の意図が適切に伝わらないことがあるんです。
逆に、意図に沿った適切な触れ方をすると、触れることによって得られる相手の安心感や立ち直ろうとする力をより大きくすることもできるのです。
小学生の時、何かのタイミングで先生が「頑張れ!」と言う言葉と共にガシ!っと肩を掴んでくれたのですが、私には驚きしかなくて。
もちろん先生は気合を入れてあげよう、励まそうとしてのことだったと思うのですが、
急な強い接触は体をこわばらせて戦闘状態にするので、より心拍数が上がり、視野は狭くなり。。。
触れることで正しく意図が伝わらないなんて、こんな残念なことありません。
レベル1の技も頼れる技になる
何かの状況に対応するために、身体を良い状態に持っていく必要があります。
そして、より良い状態にするために必要な触れ方があります。
お昼寝の時に、身体をリラックスするのをサポートする触れ方
緊張している身体を緩める触れ方
元気を出すのを促す触れ方。。。

ポリヴェーガル理論によると、興奮状態になった時にゆったりした気持ちであやしてもらう経験が
子ども時代に蓄えられることで、
成長した後も不安なこと、ストレスがかかることに対して
健全な対応ができるようになったり、落ち込みからの回復がしやすくなったりする、と言われています。
また、ASDの子どもや、HSC、彼らに関わる大人にとっても、プラスの役割を果たしてくれることがわかっています。
特に先生や支援者には、子どもと関わるプロとして、触れることも技術として身につけてほしいな、と願っています。
触れる、と言うことは誰にでも出来ること。
それだけじゃなく、上手に使いこなせば、目の前にいるその子がしなやかに生きていくための土台を作れる、頼もしいスキルなのです。
セルフケアもして、「心地よい存在」へ
触れることは、相手だけでなく、触れる人自身にも良い変化を体に与えてくれます。
セルフケアのために自分自身を大切に触れることで、興奮状態を程よいところまで落ち着かせたり、
逆に程よく高風状態に持っていくことでパフォーマンスを上げるのにも役に立ちます。
程よい状態にいる人のそばにいると、程よい状態が伝播するので、隣の人も良い状態になります。
寝てる人の隣にいると眠くなっちゃう感じ。
隣にいると、「なんか落ち着くな〜」って人、いませんか?
自分を良い状態にすることは、身近な人のためでもあると言えます。

子どもをケアする人は、自分のことを二の次にしがち。
誰かのために全振りすることも素晴らしいのですが、自分にもその愛情を注ぐことは、
必ずしも自己中心的なことではないのだ、と言うことも
ぜひ知っていただきたいことです。
タッチケア講座、ぜひ!
コミュニケーションのスキルレベル1である「触れる」ことの奥深さ、そして学び、実践していくことで強い武器になり得ること、伝わったでしょうか。
私は緊張しいで心配性、いつもドキドキソワソワしていましたが、
誰かのためにも良い状態でいること、自分も大切にすることを心に留めるようになってからは
仕事でもよく動けるようになったように感じるし、生活の中でも誰かに対してイライラしたり、
自分に対してネガティブ思考で攻めるようなことが減ってきたように思います。
私が実践していることが、(よくも悪くも)ヒントやきっかけになるかもしれない、
そう思って、タッチケア講座を開催しています。
「こんな場面で使いたい」「こういう場にしたいんだけど、タッチケアは使える?」
「私にはどの講座がいいの?」
そんな思い、ぜひ聞かせてください。その思いを形にするお手伝いをしたいと思っています。
お申し込みは下記フォームから。よろしくお願いいたします。