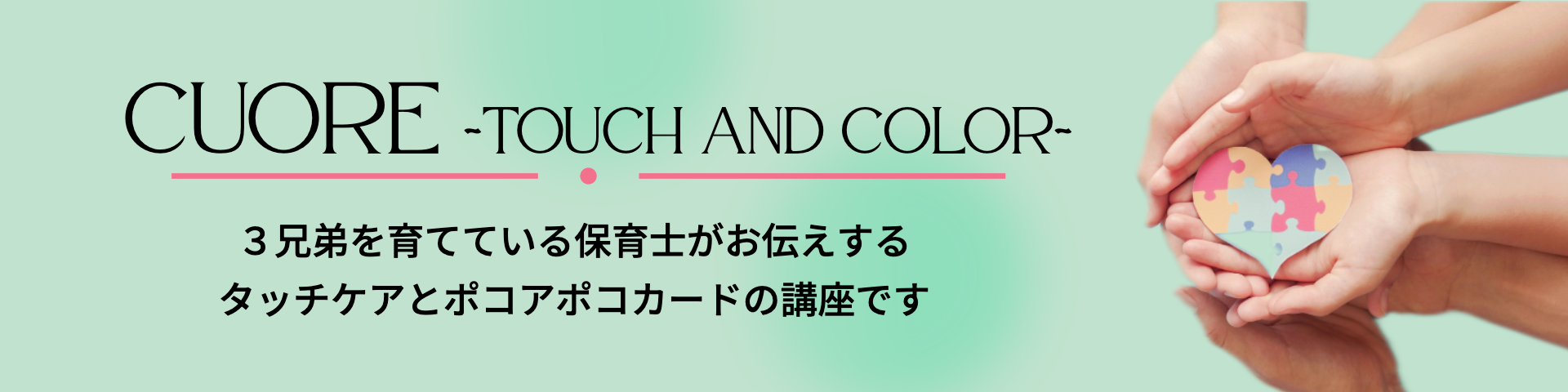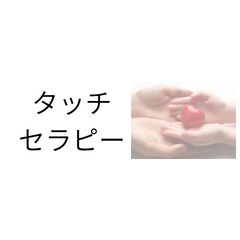「触れる」って、誰にでもできることだから、「なんでわざわざお金を払って教えてもらうの?」って思いませんか?
私もそう思っていました。
目次
先生1年目での戸惑い
なんの疑問も持たずに教員免許をとり、幼稚園に就職しました。
担任になって初めて、「え、預かってる子を、どんな感じで触っていいの?」っていう疑問が生まれてしまったのです。
それまでは、[いとこ]、とか[ボランティアのお姉さん][教育実習生]だったので、膝にのせて読み聞かせをしたり、抱っこしたり、平気でしてました。
それが、[幼稚園の担任]という立場になったら、急に距離感がわからなくなってしまったんです。(保育園だったら、もっと家庭的な距離感のままいけてたのかな、と今になると思います)
園児とスキンシップでコミュニケーションをとる、という余裕もなかったように思います。
当然1対1の関係が丁寧に積み上げられないので、学級経営がうまくいくはずもなく。
結婚を機に退職しましたが、「私、この仕事は向いてない」という思いと、「いつかまた、この現場に戻りたい」という、二つの思いがありました。
保育者向けタッチケア講座との出会い
出産をきっかけにベビーマッサージに出会い、そこから保育者向けのタッチケアを学びました。
そこで初めて、「あぁ、こうやって触れたらいいんだ」と合点がいったのです。
「不安で泣いている時はこんな風に触れていけばいい」という、関わり方のバリエーションが増えたことは、子どもに関わることについて、大きな自信になりました。
そこから、市のボランティア参加へと活動が広がり、保育園での勤務を経て、最初の職場に時間勤務の職員として再就職します。
経験則に頼らない触れ方ができる
「触れる」は誰もがしたり、されたりすることだから、皆それぞれに経験による積み重ねがあります。
また、とても本能的な行動なので、無意識的です。
でも、いろんな生活環境で育った子どもには、経験則が通用しない場合もあるのです。
「触れる=いいこと」という経験のある人は、たくさんたくさん、スキンシップを取るでしょう。
でも、「触れる」が必ずしも良い意味を持たない場合もあります。
無意識なスキンシップが、子どもにとって悲しい記憶になる場合もあります。
逆に、思いもよらない場面で「触れる」が役に立つこともあります。
残念ながら、現在の幼稚園教育要領では「スキンシップ」が保育の中でどう役に立つのか、具体的な記述はなく、「ふれあい」という曖昧な言葉でしかイメージすることはできません。
日常的に子どもに「触れる」機会の多い先生だからこそ、正しい知識を持って「触れる」を学ぶことは、園児との関係性をより良くしていくことに不可欠です。
いつか、教員養成課程の必修科目にタッチケアやタッチセラピーの内容が盛り込まれて欲しい!というのが私の願いです。